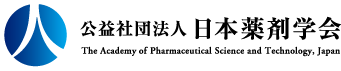このページの目次
学会賞
機能性ナノ粒子の製剤設計に基づくDDSの創製
尾関 哲也(名古屋市立大学大学院 薬学研究科)
尾関哲也博士は、製剤学分野の権威の一人であり、特にナノ粒子含有マイクロ粒子や固体分散体製剤の開発について活発に活動されている。社会実装につながる研究成果を含め顕著な業績を上げられ、その成果は115報の原著論文としてまとめられているほか、69件の招待講演を行うなど国内外で高く評価されている。教育面では、東京薬科大学と名古屋市立大学にて長年にわたり薬剤学領域の教育を担当し、多くの後進を育成されてきた。国際薬剤師・薬学連合(FIP)などの国際的組織において要職を務められ、またJ. Pharm. Sci.のEditorに就任されるなど、国際的にも活躍されている。本学会においては、会長、理事、代議員ならびに各種委員としての活動を通じて学会の発展に大きく貢献されてきた。その他、他学会や厚生労働省、PMDA、日本薬剤師会などの委員も務められ、社会的な貢献度も大きい。
功績賞
杉林 堅次(城西国際大学、城西大学)
杉林堅次博士は本学会の会長、年会長、理事、評議員、監事を歴任され、各種委員や経皮投与製剤FGの世話人などの活動を通じて、本学会の発展に大きく貢献されてきた。城西大学および城西国際大学において長年にわたり薬剤学領域の教育に従事され、留学生を含む多数の博士取得者を輩出されている。また、薬剤学に関する教科書や著書を多数執筆されており、薬剤学教育への貢献が極めて大きい。研究面では、主に薬物の経皮吸収と経皮吸収型製剤に関する顕著な研究成果を上げられ、実用化につながった研究も多い。それらの業績に対し、本学会の学会賞をはじめ種々の賞を受賞され、「製剤の達人」にも選出されている。
奨励賞
中枢疾患治療に資する多様なDDS・製剤技術の開発研究
福田 達也(和歌山県立医科大学 薬学部)
福田達也博士は、中枢疾患の治療を目的としたDDS・製剤技術の開発に向け、リポソームを始めとする脂質ナノ粒子やイオン液体、細胞療法に関する独創的な研究を実施されており、その成果は原著論文48報(うち筆頭著者19報)にまとめられている。米国Harvard大学に1年間留学され、国際学会で12回発表されるなど、国際的にも活躍されている。本学会では、超分子薬剤学FGの現執行部メンバーであり、SNPEEの組織委員長も務められたほか、年会での発表件数も多く、学会の発展に貢献されている。
薬物吸収過程における粘液層の重要性とその分子基盤解明に関する研究
岸本 久直(東京薬科大学 薬学部)
岸本久直博士は、薬物吸収過程を制御する粘液層の分子機構の解明に向けて、独創的な研究を実施されており、その成果は原著論文29報(うち筆頭著者6報)にまとめられている。英国Manchester大学に1年あまり留学され、国際学会で29回発表されており、ベストポスター賞を受賞されるなど国際的にも活躍されている。本学会では現在、代議員かつ経口吸収FGの現執行部メンバーであり、年会での発表件数も多く、学会の発展に貢献されている。
血液成分を基軸とした生体模倣型ドラッグデリバリーシステムの構築
前田 仁志(熊本大学大学院 生命科学研究部(薬学系))
前田仁志博士は、アルブミンおよび赤血球を基軸とした生体模倣型ドラッグデリバリーシステムについて独創的な研究を実施されており、その成果は原著論文57報(うち筆頭著者14報)にまとめられている。米国イェール大学に1年間留学され、最近5年間に国際学会で20回発表されるなど、国際的にも活躍されている。本学会では英語セミナー委員を務められ、年会での発表件数も多く、学会の発展に貢献されている。
タケル&アヤ・ヒグチ記念栄誉講演賞
—当期設定なし—
タケル&アヤ・ヒグチ記念賞
出口 芳春(帝京大学 薬学部)
出口芳春博士は、薬物動態学領域、特に血液脳関門(BBB)の研究に精力的に取り組んできており、独自の実験・解析法を用いることでオピオイドを含む多様な薬物のBBB透過機構を解明する顕著な成果を上げてきた。さらにヒトiPS細胞由来血液脳関門モデルを用いたBBS研究へと発展させて成果を上げ続けている。これらの成果は100報近い原著論文として発表しており、薬剤学・薬物動態学分野に対する研究上の貢献は非常に大きい。また、日本薬剤学会の評議員、学会誌「薬剤学」編集委員長・アドバイザー、国際標準医薬分業推進委員、出版委員会委員を歴任するなど、本学会活動への貢献も顕著である。
旭化成創剤開発技術賞
製剤添加剤中の反応性NOx量を新規評価指標としたニトロソアミン生成のリスクを抑えた新規製剤開発手法の確立
山本 浩之、香川 千乃、三村 尚志(沢井製薬株式会社)
本研究は、近年注目を集めている医薬品製剤中の有害物質であるニトロソアミン発生に関して、新たなリスク管理戦略を提唱するものである。具体的には、製剤中に処方される各成分に関して、新たに測定方法を規定して、反応性NOxとして包括的なNOx量を規定することに成功した。提唱される測定は、医薬品添加剤にジメチルアミンを一定量加え、生成するNDMA(N-ニトロソジメチルアミン)をLCMS/MSで定量し、得られたNDMAの量を亜硝酸イオンに分子量換算することを基本とし、反応性NOx総量を算出する。亜硝酸塩濃度のみをリスク評価指標としている現状から、全てのNOxの種類と量を特定せずに添加剤の潜在的なリスク因子として活用しようとする本手法は、新規性に富む戦略であるとともに簡便で汎用性も高い。さらに、各種添加剤に関してデータベース化も進めており、また、具体的な製剤処方により、その妥当性、有効性も確認している。以上、本研究グループは医薬品製品の製造において、注目度の高いニトロソアミン発生のリスク管理を新たな発想で追求し、実用性に求む手法を確立した。その研究成果は、今後の医薬品製造における活用が期待され、患者さん及び医療現場の安心安全のニーズにも応えるものである。
旭化成創剤開発技術賞研究助成金授与
共結晶設計によるCOVID-19治療薬エンシトレルビル フマル酸の創製
宮野 哲也、上田 廣(塩野義製薬株式会社)
本研究グループは結晶構造解析により、原薬のトリアジンとトリアゾール間の特異的な分子間相互作用が低溶解度の原因となっていることを解明した。その結果も踏まえ、化学構造に基づいて共結晶を設計することにより、フマル酸との共結晶化がエンシトレルビルの溶解度を大きく改善することを見出した。この研究成果によって、エンシトレルビルの経口製剤の開発における開発原薬として採択されることとなり、短期間での製品開発、承認に大きく貢献し、わが国発のCOVID-19治療薬の創製へと繋がった。研究としては、既存技術を効果的に活用、駆使して達成した成果と言えるが、今後、類似のケースへの応用、展開も期待される。以上のように、本研究はCOVID-19の治療と言う、医療現場、患者からの切実なニーズに応えた優れた研究成果として認められ、今後の研究展開も期待される。
旭化成創剤研究奨励賞
ヘム鉄原子価に着目したヘモグロビン製剤の創剤研究
田口 和明(慶應義塾大学 薬学部)
田口和明博士は、ヘム鉄の違いに着目して創剤素材としてヘモグロビンを活用した広範な研究で成果を上げ、多数の報告も行っている。具体的には、ヘモグロビン(Fe2+)のヘム鉄が酸化したメトヘモグロビン(Fe3+)は酸素や一酸化炭素(CO)との結合性を失うものの、硫化水素(H2S)と可逆的な結合性を示す点などの特性に着目して、ヘモグロビンを活用した研究による創剤を目指している。CO製剤やH2S供与体などいくつかの新規な創剤研究が報告されているが、その中で、亜硝酸化合物の解毒メカニズムを模倣し、その欠点を克服したシアンおよびアジド中毒解毒剤の創生などは極めてユニークで実用性も高い。また、実際に実用化へのアプローチも進んでいる。同氏による研究は、新しい着眼点で構築された創剤研究であり、新しい医薬品創成に繋がると大いに期待される。
優秀論文賞
受賞なし
創剤特別賞
受賞なし
国際フェロー称号
受賞なし
2024年度「薬と健康の週間」懸賞論文
テーマ:進歩する医療に貢献できる薬学部卒業生のあるべき姿
- 第1席 堀井 麻衣(徳島大学)
- 第2席 西野 晴香(徳島大学)
- 第3席 髙野 海人(東京薬科大学)
2024年度製剤の達人称号
- 我籐 勝彦(大塚製薬株式会社)
- 無敵 幸二(Pfizer Global Supply Japan Inc)
製剤技術伝承講習会講演当時所属